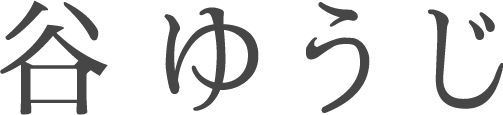登壇
9月17日、下記3項目について質疑・一般質問を行いました。質問内容を要約して掲載いたします。答弁内容につきましては後日、あらためて掲載いたします。(正式な議事録ではございませんのでご承知おきを願います。)

大津市消防局による安全を最優先とした組織文化の醸成について
令和6年8月1日、訓練中の事故で亡くなられた青木裕樹消防士に心より哀悼の意を表します。事故を決して風化させることなく、再発防止に向けた取り組みを絶え間なく継続いただくことを心から願うものです。
令和7年4月1日、大津市消防局は「訓練時における安全管理マニュアル」を新たに策定し、運用を開始しました。安全管理意識の定着に係る章には、新しい資器材、技術及び活動要領等の導入、訓練や現場活動で発生した事故事例及びヒヤリハット事例の追記、各論に記載がない訓練の安全管理体制の追記等、当該マニュアルが常に時代にあった有効なものになるよう、随時見直しを図ることが記されており、同年8月1日には、各論部分の変更・追記が行われています。過日、大津市情報公開条例の規定に基づき、同マニュアルの開示を受けました。巻頭にて、大津市消防局長が述べられている言葉を引用させていただきます。
大津市消防局は、令和6年8月1日に発生した訓練中の事故により、かげがえのない職員を失いました。
事故に至った要因は、総じて安全管理意識が欠如していたと考えられ、このことを重く受け止め、組織全体として改革に取り組んでいかなければなりません。
訓練施設、資器材、体制、意識、全てにおいて根本から見直し、重大事故を根絶することを目的とし、職員一人ひとりの安全管理に対する意識改革を図らなければならず、特に安全を最優先とした組織文化を醸成していくため、その一歩として、大津市消防局の「訓練時における安全管理マニュアル」を作成しました。
本マニュアルに記載した内容を遵守し、職員一人ひとりが安全に対して徹底した意識を持つことで安全管理体制を定着させることが重要です。
災害現場に安全な状況はなく、常に危険な環境下での活動となり、その様な現場であっても、組織は全ての職員を元気な姿で家族のもとに帰す責任があります。それは、訓練においても同様です。
事故を決して忘れてはいけない、事故を決して繰り返してはいけない、そのことを強く誓い、我々は今後、活動していかなければなりません。終わりなき安全を追及し「すべての人命を守り抜く」ために。
令和7年4月 大津市消防局長
引用は以上となります。
また、大津市消防局は令和7年度大津市議会総務常任委員会初会合における説明資料において、大津市消防局職員は、重大事故を生涯記憶に刻み、忘れない、二度と起こさない、決して風化させないよう、未来永劫にわたり職員全員に伝承する。再発防止に向けた取組を全力で推し進め、安全管理体制の構築を図る。職員全員が安全管理に対する意識の改革を図り、知識と技術の終わりなき高みを追求し続け、徹底した安全文化の醸成を図ると述べておられます。私は、これらの言葉を大津市消防局の断固たる決意、不断の努力を続けていくことへの誓いと受け止め、以下5点、質問を行います。
1点目、「訓練時における安全管理マニュアル」の実効性を高めるための取り組みについて。大津市は令和6年8月1日に発生した訓練中の事故を受けて、再発の防止を図るべく、全職員を対象にアンケートを実施されています。外部有識者によって組織された大津市消防局訓練事故検証委員会においても、安全管理体制については、現場の声を抽出したうえで、分析を進めるべきとの指摘がなされており、当該マニュアルの実効性を高めるうえにおいても大変重要な取り組みと考えます。
大津市消防局は「訓練時における安全管理マニュアル」を策定・改正するにあたり、消防隊員が訓練時に感じてきた不安や寄せられた安全性の向上に資する指摘・提言等をどの様に受け止められ、その内容に反映されたのでしょうか。今後の効果的な見直しに向けて不可欠となる、風通しのよい職場風土の構築に向けた取り組み方針とあわせて見解を求めます。
また、「訓練時における安全管理マニュアル」には、安全管理意識の定着を図るにあたり、当該マニュアル以外の各種活動マニュアルについても、現場実態に合わせたより安全な活動を目指した内容への更新を意識して訓練を実施し、随時必要な見直しを図る意識づくりに努めることが記されています。大津市消防局はこれらの取り組みを将来に渡って持続させていくため、具体的にどの様な働きかけを消防局職員に行っていかれるつもりなのか。見解を求めます。
私は、大津市消防局がどの様な姿勢、取り組みのもとで安全を最優先した組織文化を醸成されようとしているのか、消防局職員のみならず、将来に渡って広く市民と共有いただくことは、事故を風化させないためにも、大切なことであると考えます。大津市消防局が作成された「訓練時における安全管理マニュアル」を早期にホームページで公表されることについて、見解を求めます。
2点目、安全管理資器材の適正な整備について。外部有識者によって組織された大津市消防局訓練事故検証委員会において、「安全管理資器材を予算の中で組織としてしっかりと整備し、訓練できる環境を整えたうえで訓練を実施するべきである」との意見が出されています。大津市消防局は当該意見をどの様に受け止め、安全管理資器材の整備にあたられてきたのでしょうか。
3点目、訓練時における安全管理を対象とした評価のあり方について。大津市消防局は大規模災害活動対応事業の事務事業評価にあたって、激甚化・頻発化・広域化する災害に加え、テロを含むNBC災害や予測困難な感染症等にも安全・的確に対応する必要があり、これら災害から市民の生命、身体及び財産を保護するため、かつ隊員の安全確保と負担軽減のため、消防活動資機材全般の更新整備を図るとしています。令和6年9月に行われた令和5年度を対象とした当該事務事業評価では、定性評価のうち、有効性については、「適切な更新整備により安全かつ迅速な活動に繋がっている」とされ、効率性については、「的確な活動と隊員の安全確保に繋がっている」と評価されています。
大津市消防局による「訓練時における安全管理マニュアル」の策定を契機として、訓練時における安全管理のあり方についても、組織をあげて評価されることを提言するものです。今後の取り組み方針について見解を求めます。
4点目、資器材等の適正な維持管理について。「訓練時における安全管理マニュアル」においては、安全管理上の留意事項として、個人装備は、各自説明書等を熟読し、適正に使用できるよう管理すること、また、訓練内容に応じ、定められた装備及び安全器具を事前に点検し、強度劣化、破損等がないものを正しく確実に着装することなどが記されています。
修理履歴を含む点検の結果については、それぞれの所属とあわせて大津市消防局内において認識を共有されていると承知していますが、製造元のメーカーが推奨する定期点検は確実に実施されているのでしょうか。また、消防局職員が資器材等の安全性を確認するにあたり、留意点を明確にするなど、点検要領は作成されているのでしょうか。あわせて見解を求めます。
5点目、消防五訓のあり様について。平成25年3月、大津市消防局は「職責の自覚」、「厳正なる規律の保持」、「奉仕と絆の精神」、「資質の向上」、「明日への挑戦」からなる消防五訓を制定しました。令和7年版消防年報によると、全職員が目指すものを共有するとともに、消防局を偲ぶ言葉として制定されたとあります。
大津市消防局は安全を最優先とした組織文化の醸成を図るにあたり、また、令和7年度大津市議会総務常任委員会初会合で示された「重大事故を生涯記憶に刻み、忘れない、二度と起こさない、決して風化させないよう未来永劫にわたり、職員全員に伝承する」との決意と誓いを実現していくため、消防五訓をどの様に位置付けられているのでしょうか。
また、大津市消防局は消防五訓を「消防局を偲ぶ言葉」として制定したと公表されていますが、意味するところが不明確であると考えます。大津市消防局にとって、また、大津市消防局に勤務される全ての職員にとって、消防五訓はどの様な言葉なのでしょうか。安全を最優先とした組織文化の醸成に大きな影響を及ぼすものと考え、見解を求めます。
浜大津バスターミナル上屋の耐震性能と大地震発生時における天井の安全性について
1点目、構造体の安全性について。昭和56年、第36回国民体育大会、第17回全国身体障害者スポーツ大会の開催を契機として、京阪電車京津線、石坂線の浜大津駅舎の統合を経て、浜大津総合ターミナルの整備が行われました。建物の規模は地上2階建て、建築面積は900㎡、延床面積は1,800㎡です。



浜大津バスターミナル上屋の外観を撮影した写真を投影いたします。
1枚目は浜大津スカイクロス大津港側から撮影した写真、2枚目と3枚目は1階バスターミナルと2階歩行者専用通路をスカイプラザ浜大津に向かって撮影した写真です。
大津市は浜大津バスターミナルの上屋を整備するにあたり、昭和55年12月に建築主事に対して計画を通知し、建築基準関係諸法令に適合しているかの審査を受けています。都市計画部建築指導課に保存されている台帳によると、昭和56年2月には適合しているとの確認を受け、工事完了の後、同年10月には検査済証の交付を受けています。昭和56年6月1日、建築基準法施行令が改正され、耐震基準が強化されています。旧の耐震基準で設計されているのであれば、耐震性能が不足している恐れがあります。
竣工の後、当該建築敷地は道路区域に含まれたことから、今日に至るまでの間、大津市は浜大津バスターミナルの上屋を建築物としてではなく、道路構造物として維持管理を行ってこられましたが、耐震性能をどの様に評価されているのでしょうか。また、現時点で評価ができないのであれば、今後、どの様な方針のもとで耐震性能を確認されていくつもりなのか。見解を求めます。
2点目、非構造部材である天井の安全性について。明日都浜大津が竣工した平成9年度には、浜大津バスターミナルの上屋にメッシュ形状の天井材が取り付けられています。平成26年4月1日、建築基準法施行令の改正が施行され、特定天井が定義されました。特定天井とは、吊り天井であって、①居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられているもの、②高さが6メートルを越える天井の部分で、その水平投影面積が200㎡を超えるものを含む、③天井面構成部材等の単位面積質量が1㎡当たり2キログラムを超えるもの、以上のいずれにも該当するものであり、国土交通省の告示において、大臣が定める技術基準に従い、脱落防止対策を講ずべきことが定められています。



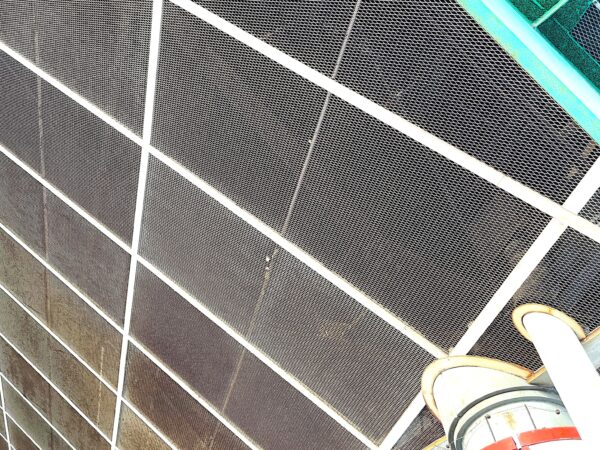
浜大津バスターミナル上屋の天井面を撮影した写真を投影いたします。この項4枚目はびわ湖浜大津駅側から撮影した写真、5枚目、6枚目は階段付近を撮影した写真、最後、7枚目は天井材をアップで撮影した写真です。
バスターミナルとびわ湖浜大津駅、浜大津スカイクロスをつなぐ2カ所の階段はそれぞれ吹き抜けに設置されています。また、天井材は多面的な屋根の形状に合わせて貼られており、勾配がついていることから、天井までの高さは測定する位置によって大きく異なります。大規模地震の発生を想定し、大津市は複雑な形状をしている浜大津バスターミナルの上屋天井の安全性をどの様に評価されているのでしょうか。点検、調査の必要性に対する認識とあわせて見解を求めます。
開設から50年目を迎えた大津市民会館の今後のあり方について
1点目、特定天井の損傷・劣化状況に対する評価と耐震対策の実現に向けた取り組みについて。令和7年3月18日、国土交通省住宅局建築指導課建築物事故調査・防災対策室ならびに市街地建築課市街地住宅整備室は各都道府県建築行政主務部局に対して、大規模空間を持つ建築物の吊り天井の脱落対策の徹底に関する依頼文を発出しました。大津市においては既にその内容を把握されていると承知していますが、市民の生命、安全に関わる重要な内容であることから、ここにその一部を要約して引用させていただきます。
建築基準法においては、東日本大震災等における天井の脱落被害を踏まえて、天井の安全性を確保するため、脱落によって重大な危害を生ずるおそれのある特定天井について、天井脱落対策に係る基準を定めるとともに、天井の劣化及び損傷の状況について定期的な点検及び報告を求めています。昨年1月に発生した令和6年能登半島地震の発生を受けて、国土技術政策総合研究所及び国立研究開発法人建築研究所が天井に関する被害情報のあった建築物を対象として実施した調査においては、天井の全面的な脱落被害は確認されませんでしたが、天井板の損傷や落下、鋼製下地材の外れ等の被害が確認されました。また、関係団体が令和6年能登半島地震の被害を受けた地方公共団体からの依頼を受けて実施した公共建築物(いずれも震度5強以上を観測した地域に存する建築物)の調査においても、天井の全面的な脱落被害は確認されませんでしたが、外観からは無被害に見える天井において、天井裏では天井を支えるクリップの外れや吊りボルトを固定するナットの緩みなどの損傷の状況が確認されました。これらの調査結果からも分かるとおり、大きな地震動を受けた吊り天井は、外観からは大きな被害が確認されない場合であっても、天井裏においてはクリップの外れやナットの緩みなどの天井を実質的に支えている部材の損傷が生じている場合があります。仮にこのような状態にある天井の改修等の対策を行わなかった場合、次に大きな地震動を受けた際には、天井の脱落につながり、最悪の場合は人命などに大きな被害を及ぼす危険性があります。このため、大規模空間を持つ建築物の吊り天井については、通常の定期的な点検時だけではなく、大きな地震動を受けた際にも緊急的に天井裏を含めた点検を行い、安全性を確認することが必要です。
引用は以上となります。
大津市民会館においては、これまでの質疑・一般質問においても指摘してきましたが、耐震改修が行われていない特定天井を有しています。昭和50年に開設されてからこれまでの間、大津市内においては平成7年に発生した阪神・淡路大震災、平成30年に発生した大阪府北部地震において、最大震度5以上の揺れが観測されています。
令和5年6月、国土交通省は日本建築行政会議に対して、同年4月に日本耐震天井施工共同組合が取りまとめた『「天井耐震診断報告書」調査研究報告書』によると、同組合が実施した天井耐震診断において、特定天井に該当するもの(682箇所)のうち、75%以上の箇所で部材の劣化・損傷が見つかったとの情報提供を行っています。これらの施設はいずれも定期調査・点検の対象となっていたものの、既存不適格建築物であることのみをもって要是正と判断され、天井裏の目視調査が適切に実施されていない恐れがあるとの指摘がなされています。
大津市は大津市民会館大ホール及びホワイエにおける特定天井の損傷・劣化状況を、建築基準法第12条に基づく点検結果を踏まえてどの様に評価しているのでしょうか。国土交通省住宅局指導課長による特定天井についての技術的助言で求められている天井裏の調査状況と安全性の確保に向けた今後の取り組み方針とあわせて答弁を求めます。
2点目、南海トラフ地震臨時情報発表時における施設管理運営のあり方について。令和7年8月、内閣府は平成31年3月に策定され、これまで2度に渡って修正されてきた「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン」を「南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイドライン」として改訂しました。令和6年8月、初めての南海トラフ地震臨時情報発表時の教訓から、巨大地震注意に関する記載の充実を図る等の修正が行われました。当該ガイドラインには、「南海トラフ地震臨時情報」が発表された場合に住民等がとるべき行動、及び地方公共団体や事業者がとるべき防災対応をあらかじめ定めておくために参考となる事項が記載されています。内閣府が公表している当該ガイドライン概要版の記述を以下、要約して引用します。
時間差をおいて発生する地震は、先発地震と後発地震の間の行動によって被害の程度が大きく変わることから、臨時情報の発表を受けて事前避難等の防災対応をとることで、後発地震が発生した場合における人的被害等の軽減が期待されます。一方、現時点の科学的な知見では、地震発生時期・規模・場所についての確度の高い予測は困難であり、臨時情報が発表されたとしても、後発の大規模地震が発生するかどうかは不確実です。
これらのことを踏まえ、当該ガイドラインにおいては、各主体が、臨時情報の種類、各地域のリスクや各業種の特徴などの実情を考慮して自らの行動を自ら決めることが重要であり、臨時情報が発表された際に戸惑うことなく防災対応をとるために、臨時情報が発表された時の行動はあらかじめ決めておくことが有効です。住民は「自らの命は自らが守る」という原則に基づき、臨時情報が発表されたときの自らの行動を自ら判断する。地方自治体・事業者は、「地域や利用者等の安全確保」「社会経済活動の継続」とのバランスを考慮しつつ、臨時情報が発表されたときの自らの行動を自ら判断し、あらかじめ決めておく。
引用は以上となります。
地方公共団体の防災対応(巨大地震警戒対応)の検討の章には、日常生活を行いつつ、一定期間、できるだけ安全な行動をとることが重要であり、住民が普段以上に地震に備えて警戒するという心構えを持つことができるよう、適切な周知啓発を行う必要があると記されています。壊れやすい建物等、危険性が高い場所をなるべく避けることがより安全な行動の事例としてあげられていますが、大津市民会館大ホール及びホワイエには、国土交通省の告示において、大臣が定める技術基準に従い、脱落防止対策を講ずべきことが定められている特定天井が存在します。特定天井は「脱落によって重大な危害を生ずるおそれがある天井」と定義づけられており、耐震改修工事が行われていないのであれば、当該ガイドラインで示される「危険性が高い場所」に該当すると考えます。
南海トラフ地震臨時情報とは、南海トラフ沿いの想定震源域で一定規模以上の地震が発生した場合等に、続けて大規模地震が発生する可能性が平常時と比べて相対的に高まった場合に発表される情報です。先発地震の発生場所や規模等によって南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)や同(巨大地震注意)等が発表され、これを受けて国は情報の種類に応じた防災対応を呼び掛けることになります。
大津市民会館においては、平成19年に耐震補強工事が実施されていますが、大規模地震の発生によって特定天井が脱落した場合、施設利用者の生命に危険を及ぼす可能性があり、円滑な避難にも影響を及ぼすことが危惧されます。大津市は施設利用者の安全を確保する観点から、南海トラフ地震臨時情報が発表された場合を想定し、大津市民会館大ホール及びホワイエの立ち入りに関して、あらかじめ方針を決めておかれるべきと提言するものです。検討されるべき事項は多岐に渡ると承知していますが、施設設置者である大津市長には、南海トラフ地震臨時情報発表時、特定天井の耐震改修工事が行われていない、大津市民会館大ホール及びホワイエについては、危険性が高い場所であることを広く伝える責務があると考えます。
大津市には大津市民会館以外にも、生涯学習センター(アトリウム・客席)、北部地域文化センター(客席)、和邇文化センター(客席)など特定天井を有する施設が数多く存在します。既存不適格扱いとなっている特定天井の脱落防止対策は、市民の安全に関わる極めて緊急性の高い改修工事であり、これまでの間、質疑・一般質問の機会を通じて早期の対応を求めてきましたが、大規模地震はいつ、どのような状況のもとで発生するか分かりません。大津市民会館をはじめとする特定天井を有する市有施設を対象とした、南海トラフ地震臨時情報発表時における管理運営方針を策定することについて、見解を求めます。
3点目、びわ湖浜大津駅周辺の魅力向上とにぎわいの創出に向けた取り組みについて。大津市は令和3年度から4年度にかけて、びわ湖浜大津駅周辺市有施設の利活用の検討に係る調査を実施しました。大津市民会館、大津公民館、旧大津公会堂、スカイプラザ浜大津、大津市立図書館を対象として、施設利用者を対象としたアンケートならびに市民アンケートが行われ、
①建物の安全性・老朽度(耐震性、老朽度や不具合の現状、バリアフリーの現状について)
②利用状況と施設機能(貸室等の利用状況と稼働率、施設機能の陳腐化・更新の必要性について)
③エリアマネジメント(施設機能の浜大津周辺エリアにおける整理・連携の可能性について)
の3つの視点に基づき、当該各施設の現況評価が行われました。大津市は大津市民会館における建物の安全性・老朽度について、「大規模改修、改築等による対応が望まれている」と評価しています。
同施設は開設されてから50年が経過しており、これまでの間、外壁改修工事や耐震改修工事、設備の修繕工事などが行われてきましたが、施設内におけるバリアフリーには課題が多く、構造上、図れる改善にも限りがあると認識しています。私の知る限り、滋賀県内においても老朽化の程度が著しい、大規模なホールを有する公共建築物です。大津市は令和4年9月16日に開催された大津市議会総務常任委員会において、今後の方向性を検討するにあたって、「考慮する点」を明らかにしています。
① 大津の文化拠点エリア、交流結節の有利性を活かす(興行適性の活用)
② 購買・飲食施設のスポット配置や市有施設との複合化を図る(周遊性の向上)
③ 駐車、エリア内移動の経路・手段の最適化を図る(駐車場不足への対応)
④ エリア内のホール機能、会議室機能を整理・再編する(機能配置の最適化)
⑤(仮称)新・琵琶湖文化館、大津湖岸なぎさ公園、大津港などとの相乗効果を高める(施設間の連携)
以上の5点です。
大津市は令和7年6月通常会議で私からの大地震・巨大地震発生時における災害対応力の強化をテーマとした議会答弁において、特定天井の耐震対策については、公共施設マネジメントの取組の中で進めており、施設のあり方検討を踏まえ、大規模改修等の対策の優先順位を見極めた上で、必要な対策を講じていくとの見解を示されています。先ほど申し述べた「考慮する点」を踏まえ、施設のあり方検討が進まなければ、耐震対策が図られていない特定天井を大津市は大津市民会館に有し続けることになると危惧するものです。
大津市はびわ湖浜大津駅の周辺エリアに新しい琵琶湖文化館が整備されることを契機として、このエリアを歴史文化の学びや文化芸術の創造の場とし、にぎわいを創出することを目指しています。また、滋賀県においては、日本一にぎわいのある「湖の港」を目指し、「大津港活性化・再整備基本構想」を策定し、滋賀県立琵琶湖文化館整備事業についても、令和9年12月の開設に向けて工事が進められています。
これまでの間、大津市はびわ湖浜大津駅周辺の魅力向上とにぎわいの創出を図るため、大津市民会館をはじめ、当該エリアに立地する市有施設の利活用と整備のあり方に係る検討をどの様な取り組みのもとで進めてこられたのでしょうか。耐震改修が行われていない特定天井を有する大津市民会館については、防災上の観点からも、早期に方向性を決定されるべきと考え、見解を求めます。