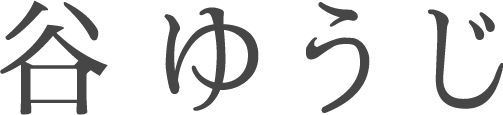登壇
6月16日、下記5項目について質疑・一般質問を行いました。質問内容と答弁内容を要約して掲載いたします。正式な議事録ではございませんのでご承知おきを願います。

〇大津市と草津市が両市共通の推奨ルールとして策定した「びわこ東海道屋外広告物ガイドライン」の効果的な周知と普及促進に向けた取り組みについて
令和7年6月1日、大津市と草津市が両市共通の推奨ルールとして策定した「びわこ東海道屋外広告物ガイドライン」の運用が開始されました。近江大橋を挟んで両市を結ぶ県道18号と東海道を対象としており、令和3年3月に策定された「びわこ東海道景観基本計画」で定める屋外広告物による景観形成の目標を踏まえ、その場所ごとのまちなみと調和した屋外広告物が並ぶことにより、魅力ある景観を守り、地域らしさを創造していくことを目的としています。当該ガイドラインについては、市民、事業者、行政の三者協働によって組織される「びわこ東海道景観協議会」において、令和3年度から令和6年度にかけて検討が重ねられてきました。
大津市と草津市による広域景観連携は平成22年4月に両市職員によって組織された「大津草津景観連絡会議」の設置がきっかけとなって始まりました。平成25年11月には「びわこ大津草津景観宣言」のもと、両市市長が会長、副会長を務める「びわこ大津草津景観推進協議会」が設立され、平成28年4月には両市議会の議決を経て、地方自治法に基づく法定協議会へ移行し、現在に至っています。また、平成29年5月には、両市市長によって東海道統一案内看板ロゴマークに係る商標登録に関する協定書が締結されています。平成30年11月には、びわこ大津草津景観推進協議会・東海道統一案内看板専門部会によって同看板設置の手引きがまとめられ、現在、同看板は宿場が形成されていた滋賀県内すべてのまちに設置されています。令和7年7月に開催される両市在住の小学生とその保護者を対象とした「景観づくりチャレンジ隊」においては、ベンガラを塗るワークショップが滋賀県建築士会の協力のもとで実施され、今年度においては、逢坂の関記念公園と野路コミュニティセンターに新たに設置される予定となっています。「びわこ大津草津景観宣言」の実現に向けた取り組みは、未来を見据えて発展的に継続されています。
びわこ東海道屋外広告物ガイドラインは推奨ルールではあるものの、びわこ東海道景観基本計画には、パートナーシップによる景観形成の推進が掲げられており、三者協働に基づく事業者の役割については、市民、行政との信頼関係を深め、景観形成への積極的な理解と協力に努めるとともに、両市の良好な景観保全に支障を及ぼすことのないよう、責任ある選択を行う必要があると明記されています。あわせて、令和7年11月1日から施行される第2次大津市景観計画においても、びわこ東海道景観基本計画で定めた草津市との連携による屋外広告物の統一的な規制ルールをはじめとして、広域的な屋外広告物の景観形成についても推進していく方針が示されています。
対象区域に現存する屋外広告物に対しては、許可期間を踏まえた早期の対応が必要となります。また、当該ガイドラインを遵守して屋外広告物を新たに設置、更新される広告主や屋外広告事業者に対しては、新たな制度や仕組みのもとで、良好な景観形成に対する貢献を顕彰することを検討されてはと提言するものです。大津市はびわこ東海道屋外広告物ガイドラインに対する広告主や屋外広告事業者からの理解と賛同が得られるよう、今後、どのような方針のもとで効果的な周知と普及促進に取り組んでいくつもりなのか。これまでの間、「びわこ東海道景観協議会」が果たしてきた役割に対する評価と今後に期待する取り組みとあわせて見解を求めます。

リンク:大津市HP 大津市・草津市の景観連携
リンク:大津市HP びわこ東海道屋外広告物ガイドラインの策定について
答弁:都市計画部長
「びわこ東海道屋外広告物ガイドライン」の効果的な周知と普及促進についてでありますが、本年6月の運用開始に向けて同ガイドラインを市ホームページへ掲載するとともに、滋賀県広告美術協同組合を通じ屋外広告事業者へ通知を行いました。今後も窓口での周知や更新時期を迎える屋外広告物の広告主に対する普及促進に努めるとともに、ガイドラインに沿った屋外広告物の申請状況の把握に努めてまいります。
なお、当該ガイドラインは本市と草津市の共通推奨ルールであることから、顕彰制度の必要性については草津市とも連携を図りながら、「びわこ東海道景観協議会」において協議することを検討してまいります。
〇大津市景観計画ガイドライン・公共サイン編の策定を契機とする公共サインの適正化に向けた取り組みについて
大津市は第2次大津市景観計画の策定に合わせて、公共サインの整備に関する基本方針や維持管理のルール等を定めたガイドラインを策定しました。令和7年11月1日から施行される予定となっています。当該ガイドラインにおける公共サインとは、大津市をはじめ、滋賀県や国、公的機関等が案内誘導・利用案内・注意喚起・啓発等を目的として、道路や公園、河川等の公共施設に設置する屋外広告物と定義されています。大津市景観計画ガイドライン・公共サイン編の策定が契機となり、サイン機能の向上や良好な景観形成が図られることに期待するものです。
令和4年6月通常会議、私は公共サインの整備更新、また、適切な維持管理を行うにあたり、景観や周辺環境との調和に配慮することに合わせ、ユニバーサルデザインの視点を踏まえながら、新たに公共サインを対象としたガイドラインを策定されることを提言しました。その際、大津市は地図や案内板等は、所管課がそれぞれの目的に応じて設置し、維持管理を行っているのが現状であり、その中には経年劣化が著しいものや、現状では表記が誤っているものがあるとの認識を示されています。加えて、令和6年2月通常会議における答弁では、全庁的に実施した公共サインの維持管理に関する調査結果を踏まえ、修繕や撤去などの進捗状況を確認した上で、所管する各所属に対して、適切な維持管理を促していく方針を示されています。
令和6年度、大津市は自らが設置し、維持管理を行っている公共サインの現況を把握するための調査を改めて実施されたと認識していますが、新たに策定された「大津市景観計画ガイドライン・公共サイン編」の対象となる公共サインの数は調査時点でどの程度あり、この内、どの程度の割合で課題があると把握されているのか。そのうえで、必要な措置を講じるにあたっては、第2次大津市景観計画における景観重点地区や大津市歴史的風致維持向上計画において重点区域に指定されている「堅田地域」「坂本地域」「大津百町地域」において、より優先的に取り組まれることを提言するものです。大津市は「大津市景観計画ガイドライン・公共サイン編」の策定を契機として、どのような方針のもとで公共サインの適正化に取り組んでいくつもりなのか。見解を求めます。
また、令和6年2月通常会議における答弁において、国や滋賀県、公共的団体を含め、十分な周知を行うことにより、その活用が図られるよう検討を進めていく方針が示されていますが、公共サインの適正化に向けて、具体的にどのような働きかけを行っていくつもりなのか。合わせて見解を求めます。
リンク:大津市HP 大津市景観計画ガイドライン 公共サイン編 【PDF】
答弁:都市計画部長
1点目の「大津市景観計画ガイドライン・公共サイン編」の対象となる公共サインの実態についてでありますが、令和6年度に実施した「公共サインの実態調査」の結果、公共サインの総数は1,758件、うち表記誤りや劣化が確認されたものは約3割の537件でありました。
次に、2点目の公共サインの適正化に向けた取り組みについてのうち、1つ目のどのような方針のもと公共サインの適正化に取り組んでいくつもりなのかについてでありますが、本年4月に、市全域の公共サインについて適正に管理するよう庁内にガイドラインを周知しました。令和7年度以降も引き続き調査を実施し、課題のあった公共サインについてフォローアップに努めてまいります。
次に2つ目の国や滋賀県、公共団体に対し公共サインの適正化に向けてどのような働きかけを行っていくつもりなのかについてでありますが、本年5月に国、県の関係機関へ案内文を送付し周知を図るとともに、当該ガイドラインを市ホームページに掲載しました。今後も機会を捉え周知に努めてまいります。
再質問
公共サインの適正化に向けた取り組みについてのうち、1点目についてです。非常に数が多いと認識させていただきました。全市域を対象にフォローアップされていくということについては、そうしていただきたいと願うものですが、計画的に対応いただけないと、全市的な改善に繋がっていかないのではと懸念をいたします。改めてこの点を踏まえて答弁求めます。
答弁:都市計画部長
約3割の問題になったところについて、計画的な対応をすべきだというお尋ねだったと思います。昨年度実施いたしました実態調査につきましては、その数の把握とともに、対応方法についても各課に確認しております。該当の537件のうち、約7割にあたる346件につきましては、改修または撤去の対応方針が決まっているとの回答が寄せられましたので、今後、計画的に改善が図られていくものと考えており、また、今年度の実態調査におきましてフォローアップに努めてまいります。
〇中小企業・小規模事業者によるICT・デジタル技術を活用した業務改革とDXの推進に資する支援のあり方について
1点目、デジタル化セミナーの開催に要する事業費補助のあり方について。人手不足、事業拡大、働き方改革、事業継承など、中小企業・小規模事業者が直面される経営課題は多岐に渡ります。大津市は令和5年6月通常会議における答弁において、生産年齢人口が減少し、ますます人材確保が困難となる中、小規模事業者が生産性を向上させるためには、業務の効率化に繋がるデジタル化へ取り組むことが重要であるとの認識を示されています。また、本市の小規模事業者においては、業種や業態により、ICT、デジタル技術への関心や理解度、業務改善、効率化への効果が異なるため、導入に消極的な事業者も少なくないと商工団体等の関係機関から伺っており、こうしたことから、事業者の課題やニーズを把握するために実施している事業者ヒアリングにおいて、デジタル化に関する課題等についても聞き取るとともに、引き続き関係機関と連携し、より効果的な推進施策について検討していくとの方針をあわせて示されています。
大津市は中小企業者が社会経済情勢の変化に対応し、デジタル技術を活用した経営課題の解決に取り組むことを促進し、もって中小企業者の経営の効率化、事業の高度化及び生産性の向上を図ることを目的として、デジタル化セミナーの開催に要する費用を補助する制度を設けています。3以上の中小企業者を受講者として実施するものであること、受講者が自らデジタル技術を実地に体験することを通じて必要な知識を得られる方法で実施するものであること、専ら営業活動を行うことを目的として実施するものでないこと、大津市から他の制度による補助金等の交付を受けていないことを補助対象事業の要件とされており、上限額は30万円、補助率は補助対象経費に対して10分の10と設定されています。
令和5年度に事業が開始されて以降、昨年度までの2年間で市内商店街や商工会などを含む計7事業に対して補助が行われましたが、いずれの年度も措置された予算額の執行には至りませんでした。初年度は300万円の予算が措置されていたものの、前年度からは執行実績を踏まえて90万円に減額されています。大津市は当該事業に対する中小企業者のニーズをどの様に評価されているのでしょうか。
また、大津市はデジタル化セミナーを受講された中小企業者が現在、どの様な課題と向き合われながらICT・デジタル技術を活用した業務改革とDXの実現に取り組まれようとされているのか、アンケート調査や主催者からの聞き取りなどを通じて把握されているのでしょうか。当該事業は中小企業者の経営の効率化、事業の高度化及び生産性の向上を図ることを目的としていることを踏まえ、見解を求めます。
2点目、滋賀県との効果的な連携のあり方について。大津市は令和6年3月に策定した「大津市DX戦略」において、「中小企業・小規模事業者のDX推進支援」を掲げており、DX推進を目指している、あるいはDXへの適応に不安がある市内の事業者に対し、事業活動におけるデジタル技術の活用に向けた支援を進めていく方針を示しています。また、滋賀県においては、令和7年3月に「滋賀県DX推進戦略」を改訂され、「滋賀県DX官民共創サロン」において、デジタルトランスフォーメーションでお困りの方と専門家をマッチングさせ、県全体のDX推進を促進する方針を掲げています。令和7年度からの3年間で取り組む事項として、「中小企業を支えるデジタルシフトと人材育成の推進」が掲げられており、「2030年の滋賀の姿」として、「中小企業等においてもデジタル技術の進展やその利活用が成長の機会として捉えられ、デジタル化の取組が加速化するだけでなく、デジタル技術を活用して、商品・サービスの高付加価値化や生産性向上が図られ、また、高い競争力を有するビジネスモデルを構築する企業が増加している」と示されています。
大津市は今後、どの様な方針のもと、滋賀県と連携強化を図りながら中小企業者・小規模事業者によるICT・デジタル技術を活用した業務改革とDXの実現に資する支援に取り組んでいくつもりなのか。これまでの取り組みに対する評価とあわせて答弁を求めます。
3点目、伴走支援の充実に向けた取り組みについて。中小企業・小規模事業者がICT・デジタル技術を活用した業務改革やDXの推進に取り組むにあたり、システムの開発や導入に要する初期費用を確保し、将来に渡って必要となるランニングコストを見込むことは、経営者にとって大変大きな決断となります。物価高騰など厳しい経営環境のもと、投資に見合う効果が得られるには一定の期間が必要となることから、経営計画や経営戦略を新たに策定し、また、見直す必要に迫られることも想定されます。
経理や申告手続のデジタル化はもとより、経営者にとって身近な相談相手である税理士や社会保険労務士は経営改善を図る上において大変大きな存在です。ICT・デジタル技術を活用した業務改革やDXの推進に取り組む中小企業・小規模事業者への伴走支援の充実に取り組んでいただけるよう、大津市内で活動されているそれぞれの職能団体と連携強化を図られることについて、見解を求めます。
答弁:産業観光部長
1つ目の当該事業に対する中小企業者のニーズの評価についてでありますが、過年度の事業者ヒアリング等からニーズは高いと認識しております。一方で、執行実績が伸びていない要因としては、補助対象者の要件や講師の選定など、制度の利用しにくさがあると考えております。
2つ目の、受講された中小企業者のデジタル化への課題と取組の把握についてでありますが、受講された事業者からは、デジタル化に関する具体的な学びを通じて理解が深まったとの報告を受けており、その結果、経営改善につながったと考えています。
2点目の、滋賀県との効果的な連携のあり方についてでありますが、国や県がデジタル化に係るハード面の支援施策を実施されていたことから、本市においてはソフト面の支援策として本制度を設計しました。これまでの取組においては、商店街連盟で実施されたSNSを活用した販売戦略セミナーや、3者合同による会計ソフトの勉強会など、事業者のニーズに応じた施策を推進できたと評価しております。
今後の県との連携については、中小企業者のデジタル化への支援の方向性を共有し、県と市の役割を明確にしながら連携を図ってまいります。
3点目の、伴走支援の充実に向けた取組についてでありますが、事業者の身近な相談相手である税理士や社会保険労務士が所属されている職能団体への意見聴取など、職能団体との連携強化の手法について調査研究してまいります。
再質問
細目2、滋賀県との効果的な連携のあり方についてです。ただいま、答弁で滋賀県と方向性を共有されて、連携を図っていかれる方針をお示しになられました。現時点で方向性を共有するための協議や議論はどの程度されているのでしょうか。現状をお聞かせください。
答弁:産業観光部長
滋賀県との効果的な連携のあり方について、現時点で具体的な協議、また、連携をしているのかについてご質問をいただいたと存じます。現在、具体的な会議体を設けたりしての協議は行っておりませんが、県とそして、本市の役割を明確にし、そして、それぞれの方向性や実施施策などを共有化することは非常に大切なことであると考えております。今後、必要に応じてそういった会議、あるいは意見交換をしてまいりたいと考えております。
〇大地震・巨大地震発生時における災害対応力の強化に向けた取り組みについて
1点目、大津市災害時受援計画の実効性を高めるための取り組みについて。令和7年3月、大津市は能登半島地震を教訓とし、災害時の人的、物的支援の受入れをより実効的なものとするため、被災地への職員派遣による支援で得た知見や気づきなどを大津市災害時受援計画に反映するべく、同計画の修正が行われました。受援対象業務の実効性を高めるための取り組みとして評価するものですが、災害対応に不慣れな職員であっても効果的に運用できる計画となるよう、今後も必要に応じて見直しを行っていく必要があります。
業務継続計画と災害受援計画は災害対応の両輪となる計画であり、国による応急対策職員派遣制度や関西広域連合による関西広域応援・受援実施要綱といった広域的な応援調整の仕組みと連携したものとして、計画内容に整合性があること、また、同時並行的に運用可能であることが災害対応の実効性を高めるためには不可欠であることなどから、兵庫県神戸市においては令和3年8月、業務継続計画と災害受援計画を統合した「災害時業務継続・受援計画」を策定されました。そのうえで、災害対応を行う職員が災害業務全般の全体像をとらえ、その実務をサポートするものとして「災害対応工程管理システム」を導入されており、あらゆる災害種別への対応手順の確認、応援要請と受援対応、業務の進捗確認を一元的に運用していくことを目指しておられます。導入翌年度における神戸市議会決算特別委員会において、委員からの導入の目的と効果、期待される効果に対する質疑に対して、神戸市は災害対応に係る各種計画やマニュアルが散在していることで、必要となる資料の検索が困難な状況であったり、また、各局室区の担当する災害対応業務の関連性が把握しづらいといった課題があったものの、システムの導入により、各種計画やマニュアルのプラットフォーム化、災害対応業務の関連性や進捗状況の可視化が図られ、災害対応力の強化につながるものと期待していると見解を示されています。
神戸市が業務継続計画と災害受援計画を統合した「災害時業務継続・受援計画」を策定され、また、「災害対応工程管理システム」を導入されるに至った経緯について理解を深めることは、大津市災害時受援計画を効果的に運用するうえで有益であると考えます。神戸市の課題認識と取り組みに対する大津市の見解を求めます。
また、大津市は受援力向上に向けた取り組みとして、本計画の推進、見直し、受援対象業務シートの管理、受入体制の充実、災害時応援協定の実効性強化、受援に関する研修、訓練の実施を掲げています。このうち、受援に関する研修、訓練の実施については、「本市の受援力を向上させるため、地方公共団体をはじめとした関係団体や、協定締結事業者等からの受援を想定した研修や図上訓練等を定期的に実施する。」と明記されていますが、計画策定からこれまでの間、どの様な研修や図上訓練が行われてきたのでしょうか。受援対象業務シートの活用状況とあわせて答弁を求めます。
2点目、災害時対応人員管理支援システム(SHIFT)の活用について。熊本県熊本市は業務継続計画と災害時受援計画を策定されるにあたり、内閣府が被災自治体における災害対応時の業務量と災害対応条件により必要人員をシミュレーションできるシステムとして開発した「災害時対応人員管理支援システム(SHIFT)」を活用されています。大津市が平成28年10月に業務継続計画を策定した時点において、内閣府は同システムを開発しておらず、大津市は最大の被害想定を前提として、非常時優先業務と必要人員及びそれに伴う不足人員を独自に算出されています。
滋賀県は平成31年3月に策定した滋賀県災害時受援計画のなかで、各市町に対して、業務継続計画、受援計画等を作成するとともに、応援を必要とする人数については、内閣府の「災害対応人員管理支援システム(SHIFT)」等を利用し、職種、人数、期間を算定しておくことを求めています。また、内閣府が令和7年4月に改訂した「市町村のための人的応援の受入れに関する受援計画作成の手引き」においても、応援に必要な業務内容と必要人数の見積りについて、内閣府が作成したソフト「災害対応人員管理支援システム(SHIFT)」によるシミュレーションを活用することも平時から検討しておくことと記されています。
私は令和2年2月通常会議において、熊本市における取り組みも参考にされながら、あらためてこのシステムを活用されることを提言しました。その際、大津市は「当該システムでは、災害対応の基礎データをあらかじめ入力しておくことで、災害の規模や被害の程度、状況に応じた対応人員と復旧予定日の算出が可能となること、また応援要請人数の把握を迅速に行えるといった点から、大変有効なシステムであると考えております。今後、本システムの他都市の取組や導入状況を調査し、検討してまいります。」と見解を示されています。業務継続計画ならびに受援計画の実効性を高めるため、内閣府の「災害対応人員管理支援システム(SHIFT)」を活用することについて、これまでの検討経過とあわせて答弁を求めます。
3点目、高圧発電機車を活用した水道施設の停電対策の実効性を高めるための取り組みについて。大津市は5箇所の浄水場と67箇所の加圧施設を有しており、このうち13箇所は高圧受電施設となっています。大地震・巨大地震の発生に伴い、電力供給が停止した場合に備え、大津市企業局はリース契約によって、500KVAの高圧発電機車2台を柳が崎浄水場に配備しています。燃料については大津市が購入した非常用燃料5,000リットルが契約を締結する事業者によって備蓄されており、高圧発電機車を稼働させる際には、タンクローリー車によって配備先に配送される契約となっています。
令和7年度水道事業会計の予算審査時においては、長期停電を想定した訓練の具体的な計画は持たれていないとのことでしたが、以前に発生した大規模な停電での経験を踏まえ、その必要性について言及がなされました。水道施設を対象とした停電対策の実効性を高めるため、委託事業者と連携を図りながら高圧発電機車の稼働を想定した訓練をできるだけ早期に実施されることを提言するものです。訓練を通じて課題を抽出し、改善を図ることで災害対応力の強化につなげていただきたいと考え、見解を求めます。
4点目、市有施設における特定天井の脱落防止対策について。私は令和6年8月通常会議において、特定天井に係る法令の改正施行から10年以上が経過したにも関わらず、数多くの市有施設で対策が講じられていない現状を重く受け止め、大津市は危機感をより一層強く持たれるべきであると指摘しました。特定天井とは、吊り天井であって、①居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられているもの、②高さが6メートルを越える天井の部分で、その水平投影面積が200平方メートルを超えるものを含む、③天井面構成部材等の単位面積質量が2キログラムを超えるもの、以上のいずれにも該当するものであり、国土交通省の告示において、大臣が定める技術基準に従い、脱落防止対策を講ずべきことが定められています。
平成23年3月に発生した東日本大震災においては、大規模空間を有する建築物の天井が脱落する事例が多数発生し、かつてない規模で甚大な被害が生じています。これまでの間、大津市において必要な改修工事が行われたのは、耐震補強工事にあわせて対策を講じられた和邇市民体育館のみであり、同体育館を除く11の市有施設、具体的には市民会館(大ホール・ホワイエ)、瀬田公園体育館(アリーナ)、仰木太鼓会館(大ホール)、葛川少年自然の家(プレイルーム・ホールB)、和邇文化センター(客席)、生涯学習センター(アトリウム・客席)、北部地域文化センター(客席)、におの浜ふれあいスポーツセンター(ピロティ・アリーナ)、伝統芸能会館(劇場)、和邇図書館(閲覧室)、北部学校給食共同調理場(調理室)については、できるだけ早期に脱落防止対策を講じる必要があります。令和7年度においては、瀬田公園体育館、和邇図書館の改修工事に向けた設計費用が措置されていますが、安全確保に向けた取り組みを一層加速いただきたいと願うものです。
大津市は令和6年8月通常会議における答弁において、公共施設マネジメントの取組の中で、施設としての在り方検討に必要な評価方法を整理しており、これを踏まえて大規模改修等の対策の優先順位についても見極めをしていく予定であること、また、この中で特定天井の改修も検討していくとの方針を示されました。令和7年3月に策定された「大津市行政改革プラン2025」における位置づけについても見解を述べられていますが、既存不適格扱いとなっている特定天井の脱落防止対策は市民の安全に関わる極めて緊急性の高い改修工事です。今後、大津市はどの様な方針のもとで市有施設における特定天井の脱落防止対策に取り組んでいくつもりなのか。緊急性に対する認識と今日までの脱落防止対策に対する評価とあわせて見解を求めます。
答弁:危機管理監
1点目の大津市災害時受援計画の実効性を高めるための取り組みについてのうち、1つ目の神戸市の課題認識と取り組みに対する大津市の見解についてでありますが、市役所庁舎の被災による機能障害や行政機能の喪失、職員も被災者であることによる初動体制構築の困難さなどの実体験から得た課題認識からの取組は、同じ防災を担う行政組織として学ぶものが多いと考えております。
2つ目の受援計画策定からこれまでの間、どの様な研修や図上訓練が行われてきたのか及び受援対象業務シートの活用状況についてでありますが、実働訓練である大津市総合防災訓練をはじめ、災害対策本部員研修や災害時応援協定に基づく関係機関との意見交換会などを実施してまいりました。
次に、2点目の災害時対応人員管理支援システムの活用についてでありますが、当該システムが一定有効であることは本市も認識しておりますが、その後業務継続計画や災害時受援計画の大規模見直しの機会がなかったことから、当該システムの活用には至っておりません。しかしながら、滋賀県が近年中に防災アセスメント調査を実施する予定であり、その結果を踏まえた本市計画の改訂の際には、当該システムの導入について改めて検討してまいりたいと考えております。
答弁:公営企業管理者
3点目の高圧発電機車を活用した水道施設の停電対策の実効性を高めるための取組についてでありますが、令和6年10月に高圧発電機車2台を柳が崎浄水場に配備し、企業局内の関係課に対する説明会および、日本水道協会関西地方支部、同滋賀県支部等の合同訓練の際に、発電機の起動確認等を行ったところです。
今年度においては、市総合防災訓練の日程に合わせて、新瀬田浄水場で受託事業者と連携を図りながら、浄水場の停電を想定した訓練を実施する予定をしております。訓練の実施にあたっては、まずは、迅速な復旧体制の構築ならびに、職員の高圧発電機車の運用技術の習熟を図るとともに、停電から復電までの一連のプロセスを確認しながら、課題の把握に努めてまいります。
答弁:総務部長
4点目の市有施設における特定天井の脱落防止対策についてでありますが、大地震等に備えて対策を講じる必要があるものと認識しているところです。このため、特定天井の改修については、長寿命化改修時に合わせて行うなどの対応を検討するよう、平成27年度に各部局に通知しているところであり、特定天井を有する12施設のうち、1施設の対策を完了し、今年度、2施設の実施設計に着手する予定です。
現在、公共施設マネジメントの取組の中で進めている、施設の在り方検討を踏まえて大規模改修等の対策の優先順位を見極めた上で、必要な対策を講じてまいります。
再質問
大津市災害時受援計画の実効性を高めるための取り組みについてのうち2点目です。計画を作成された時点において、想定されていた訓練、また、行うべきと考えておられた訓練がどの程度実施されているのかを確認させていただき、より実効性を高めていただくため、受援対象業務シートを効果的に活用いただき、また、必要に応じて更新していただく必要があるのではないかとの認識のもとで質問させていただきました。
あらためてお伺いさせていただきますが、受援対象業務シートの活用、しっかり行われていると認識されているのでしょうか。お聞かせください。
2点目、細目4の市有施設における特定天井の脱落防止対策についてです。長寿命化の工事に合わせて実施なされる方針を改めてお示しいただきました。長寿命化工事に着手いただける期間については、施設様々であると認識しています。早急に対応していただく必要があると考えますが、長寿命化の工事の優先順位について、特定天井を有しているか、いないかということを考慮されるのでしょうか。あらためて見解を求めます。
答弁:危機管理監
図上訓練ならびに受援対象業務シートの活用についてのあらためてのご質問と考えております。図上訓練につきましては、実際、被災時の受援については、災害対策本部の体制で実施させていただくことになります。例年、災害対策本部の体制整備時には、基本研修を行っておりまして、また、総合防災訓練の際には、受援までを想定した内容とまではいきませんけれども、地区防災対策本部訓練などにおいて、図上訓練を実施しております。
また、図上訓練につきましては、実際に計画策定時に、当然、計画に記載した際には、有効であるというふうに考えて記載したものでありまして、その考えは現時点でも同じでございます。しかしながら、受援計画そのものの目的について、当市が被災時に災害対応、避難所運営、復旧業務の各団体からの支援を受けつつ、できるだけ混乱なく円滑に進めるためのものでありまして、計画策定から現在までの間、その目的のために必要なこと、マニュアルの未整備部分についての整備推進であったり、実地研修などを順次実施しているところでございます。
受援対策業務シートにつきましては、現在、業務単位に48業務を定めております。まずこのシートが実効性を伴うよう、現時点で一部未整備である運用マニュアルの整備に努めて参りたいと考えております。今後、大津市の総合防災訓練や、各部局で実施される研修や訓練などにおいて、有効なシートを活用した訓練の実施方法など調査研究をして参りたいと考えております。
答弁:総務部長
特定天井の優先順位というご質問であったかと思います。昨年5月に総務省からアドバイザーの派遣を受けまして、現在、施設の評価方法の検討を行っているところでございます。具体的には施設につきまして、あり方検討を行う施設、そして、今後使用し続ける施設の別を判断するための評価を行っておりまして、現時点におきましては、建築年あるいは床面積などによる1次評価により選別を行って、具体的なあり方検討を実施するための2次評価の条件とあわせて検討しているところでございます。
具体的には、施設の老朽化や使用度などの経済的価値、そして、施設目的や利用者満足度などの社会的価値、そして構造、安全や劣化度などの技術的価値、こういった3つの評価軸による評価を考えているところでございます。そういった中で、現在、詳細な評価項目や具体的な考え方などを整理しているところでございます。12条点検の結果なども評価項目には含めておりますが、特定天井については、他の点検結果等よりも重視するべき項目として扱うことを考えております。
〇皇子が丘公園と皇子山総合運動公園の魅力向上に向けた取り組みについて
1点目、庁舎整備に伴う皇子山総合運動公園のあり方に関する検討について。現在、大津市においては、都市公園である皇子山総合運動公園の一部に庁舎を整備する方針を踏まえ、同公園のあり方に関する検討が進められています。庁舎整備基本計画案では皇子山総合公園のあり方検討について、以下のように説明されています。「皇子山総合運動公園については、別所合同宿舎用地(国)に代替公園を整備することで、交流の創出などによるまちづくりの効果が期待できます。代替公園の整備に関しては、庁舎整備の進捗に合わせて検討を行います。また、JR大津京駅からのアプローチ動線やプロムナード、エントランス機能を考慮しながら、皇子山総合運動公園の回遊性の向上や防災利用の観点を踏まえ、皇子山総合運動公園のあり方について別途検討します。」引用は以上となります。
大津市は庁舎整備基本計画の策定にあたり、「健康・育み・歴史文化のまちづくりの拠点となる公園と一体となった庁舎」を基本構想で定める基本コンセプトに追加のうえ、これに基づく基本方針として、「山から琵琶湖へ至る豊かな自然や歴史文化を基礎に、皇子山総合運動公園を中心にスポーツや健康づくりの拠点となる庁舎」、「市民の交流や子どもの健やかな成長を育むまちづくりの拠点となる庁舎」、「新庁舎と公園を一体的に活用した交流の創出などによるまちづくりの拠点となる庁舎」を掲げています。令和7年度公共施設対策特別委員会初会合において、大津市からは、具体的な公園の整備内容について示すものでなく、検討を進めていくにあたってのロードマップを示すものとの趣旨で説明がなされましたが、皇子山総合運動公園のあり方に関する検討はこれらの実現に大きな影響を及ぼすものとなります。
大津市都市計画マスタープランにおける中部地域の地域別構想においては、市民等のレクリエーション活動や健康増進などに努めるため、皇子が丘公園内におけるスポーツ施設の充実を促進する方針が掲げられています。また、第4次大津市緑の基本計画においては、都市公園等のマネジメントの強化と多機能化が掲げられており、都市計画マスタープランにおいても、大津京駅周辺においては、皇子が丘公園などの既存ストックの維持・充実を図る方針が示されています。かねてから申し述べてきましたが、庁舎整備に伴う皇子山総合運動公園のあり方については、近接する皇子が丘公園と公園の魅力を相乗的に向上できるよう、検討を進められるべきと考えます。大津京駅周辺におけるまち全体の魅力創造につながる、皇子山総合運動公園、皇子が丘公園のグランドデザインを市民に示していただきたいと考え、見解を求めます。
2点目、バリアフリーの推進に向けた取り組みについて。大津市は令和7年3月に大津市移動等円滑化促進方針の策定と大津市バリアフリー基本構想の改定を行いました。この度、JR大津京駅・京阪大津京駅周辺地区については、移動等円滑化促進地区と重点整備地区に設定されており、都市公園である皇子が丘公園、皇子山総合運動公園については、生活関連施設に設定されています。大津市バリアフリー構想(実行計画)において、同地区における都市公園のバリアフリー化については、施設設置管理者において継続協議されると示されていますが、皇子が丘公園体育館、皇子が丘公園においては計画の策定にあたり、バリアフリー推進協議会構成員参加のもとでバリアフリー化の必要性を理解し、共有することを目的としてまち歩きが実施されています。
私は令和6年8月通常会議において、誰もが安心して安全に利用できる皇子が丘公園であるために必要な取組みをテーマに質疑・一般質問を行いました。その際、テニスコートに近接する駐車場については、舗装面の劣化が著しく、障害者のための国際シンボルマークも消えかかっていることを指摘しました。過日、あらためて現状を確認してきましたが、早急に改善を図られるべきとあらためて指摘するものです。また、皇子山総合運動公園においては、石板が敷設されている陸上競技場側のエリアが常態的に駐車スペースとなっています。施設出入口附近に障害者のための国際シンボルマークが表示された看板が設置されているものの、駐車区画は明示されておらず、周囲には根上がりによる段差もあることから、バリアフリーの必要性があると承知しています。
現在、バリアフリー基本構想における特定事業の設定に向けて検討を進められていると認識していますが、大津市は皇子が丘公園と皇子山総合運動公園におけるバリアフリーの現状をどの様に評価し、今後、どの様な方針をもって改善を図られようとしているのか。利用者の安全に関わる駐車場とその動線については、より早急な対応が必要と考え、見解を求めます。
3点目、広大な敷地を有する皇子が丘公園の案内地図を作成し、広く公開することについて。皇子が丘公園は昭和36年に大蔵省から無償譲与を受けて開設された大津市を代表する総合公園であり、体育館やテニスコートなど、年間を通じて多くの市民が利用する運動施設が整備されています。およそ16haの面積を有しており、駐車場についても複数整備されているものの、市民や来訪者に対して公園施設の全容を分かりやすく伝える案内地図は作成されていません。バリアフリー化に関する情報とあわせて掲載され、大津市のホームページを通じて広く公開されることを提言するものです。このことについて見解を求めます。
答弁:都市計画部長
1点目の庁舎整備に伴う皇子山総合運動公園のあり方に関する検討についてでありますが、現在、公園と一体となった庁舎整備に向け、大津市庁舎整備基本計画を踏まえつつ、皇子山総合運動公園及び皇子が丘公園の在り方検討に向けたロードマップを作成しているところであります。一方で、庁舎整備基本計画(案)では、今般の建築費の高騰により、庁舎整備の概算事業費が増加しており、現時点で庁舎整備を進めた場合の地方債の償還に伴う財政負担は、将来にわたって本市の財政運営に大きな影響を与える懸念が示されていることから、この点も踏まえた検討が必要であると考えております。
2点目のバリアフリーの推進に向けた取り組みについてでありますが、皇子が丘公園及び皇子山総合運動公園につきましては、トイレの洋式化や経路の段差等の改善が必要であると認識しております。まずは、バリアフリー基本構想に基づき、利用頻度の高いトイレのバリアフリー化を優先して整備を進めていく考えであり、令和7年度は皇子が丘公園のトイレのバリアフリー化を実施してまいります。
3点目の皇子が丘公園の案内地図を作成し、広く公開することについてでありますが、現在、皇子が丘公園の敷地内に案内地図を掲示しております。公園施設の全容が分かる案内地図の作成や市ホームページで周知することは、公園利用者の利便性の向上に寄与するとは考えますが、他の都市公園においても同様であることから、現時点で設置の予定はありません。