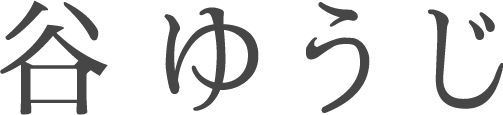開設から50年目を迎えた大津市民会館の今後のあり方について( R7. 8)
質問
1点目、特定天井の損傷・劣化状況に対する評価と耐震対策の実現に向けた取り組みについて。令和7年3月18日、国土交通省住宅局建築指導課建築物事故調査・防災対策室ならびに市街地建築課市街地住宅整備室は各都道府県建築行政主務部局に対して、大規模空間を持つ建築物の吊り天井の脱落対策の徹底に関する依頼文を発出しました。大津市においては既にその内容を把握されていると承知していますが、市民の生命、安全に関わる重要な内容であることから、ここにその一部を要約して引用させていただきます。
建築基準法においては、東日本大震災等における天井の脱落被害を踏まえて、天井の安全性を確保するため、脱落によって重大な危害を生ずるおそれのある特定天井について、天井脱落対策に係る基準を定めるとともに、天井の劣化及び損傷の状況について定期的な点検及び報告を求めています。昨年1月に発生した令和6年能登半島地震の発生を受けて、国土技術政策総合研究所及び国立研究開発法人建築研究所が天井に関する被害情報のあった建築物を対象として実施した調査においては、天井の全面的な脱落被害は確認されませんでしたが、天井板の損傷や落下、鋼製下地材の外れ等の被害が確認されました。
また、関係団体が令和6年能登半島地震の被害を受けた地方公共団体からの依頼を受けて実施した公共建築物(いずれも震度5強以上を観測した地域に存する建築物)の調査においても、天井の全面的な脱落被害は確認されませんでしたが、外観からは無被害に見える天井において、天井裏では天井を支えるクリップの外れや吊りボルトを固定するナットの緩みなどの損傷の状況が確認されました。これらの調査結果からも分かるとおり、大きな地震動を受けた吊り天井は、外観からは大きな被害が確認されない場合であっても、天井裏においてはクリップの外れやナットの緩みなどの天井を実質的に支えている部材の損傷が生じている場合があります。
仮にこのような状態にある天井の改修等の対策を行わなかった場合、次に大きな地震動を受けた際には、天井の脱落につながり、最悪の場合は人命などに大きな被害を及ぼす危険性があります。このため、大規模空間を持つ建築物の吊り天井については、通常の定期的な点検時だけではなく、大きな地震動を受けた際にも緊急的に天井裏を含めた点検を行い、安全性を確認することが必要です。
引用は以上となります。
大津市民会館においては、これまでの質疑・一般質問においても指摘してきましたが、耐震改修が行われていない特定天井を有しています。昭和50年に開設されてからこれまでの間、大津市内においては平成7年に発生した阪神・淡路大震災、平成30年に発生した大阪府北部地震において、最大震度5以上の揺れが観測されています。令和5年6月、国土交通省は日本建築行政会議に対して、同年4月に日本耐震天井施工共同組合が取りまとめた『「天井耐震診断報告書」調査研究報告書』によると、同組合が実施した天井耐震診断において、特定天井に該当するもの(682箇所)のうち、75%以上の箇所で部材の劣化・損傷が見つかったとの情報提供を行っています。これらの施設はいずれも定期調査・点検の対象となっていたものの、既存不適格建築物であることのみをもって要是正と判断され、天井裏の目視調査が適切に実施されていない恐れがあるとの指摘がなされています。
大津市は大津市民会館大ホール及びホワイエにおける特定天井の損傷・劣化状況を、建築基準法第12条に基づく点検結果を踏まえてどの様に評価しているのでしょうか。国土交通省住宅局指導課長による特定天井についての技術的助言で求められている天井裏の調査状況と安全性の確保に向けた今後の取り組み方針とあわせて答弁を求めます。
2点目、南海トラフ地震臨時情報発表時における施設管理運営のあり方について。令和7年8月、内閣府は平成31年3月に策定され、これまで2度に渡って修正されてきた「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン」を「南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイドライン」として改訂しました。令和6年8月、初めての南海トラフ地震臨時情報発表時の教訓から、巨大地震注意に関する記載の充実を図る等の修正が行われました。当該ガイドラインには、「南海トラフ地震臨時情報」が発表された場合に住民等がとるべき行動、及び地方公共団体や事業者がとるべき防災対応をあらかじめ定めておくために参考となる事項が記載されています。内閣府が公表している当該ガイドライン概要版の記述を以下、要約して引用します。
時間差をおいて発生する地震は、先発地震と後発地震の間の行動によって被害の程度が大きく変わることから、臨時情報の発表を受けて事前避難等の防災対応をとることで、後発地震が発生した場合における人的被害等の軽減が期待されます。一方、現時点の科学的な知見では、地震発生時期・規模・場所についての確度の高い予測は困難であり、臨時情報が発表されたとしても、後発の大規模地震が発生するかどうかは不確実です。
これらのことを踏まえ、当該ガイドラインにおいては、各主体が、臨時情報の種類、各地域のリスクや各業種の特徴などの実情を考慮して自らの行動を自ら決めることが重要であり、臨時情報が発表された際に戸惑うことなく防災対応をとるために、臨時情報が発表された時の行動はあらかじめ決めておくことが有効です。
住民は「自らの命は自らが守る」という原則に基づき、臨時情報が発表されたときの自らの行動を自ら判断する。地方自治体・事業者は、「地域や利用者等の安全確保」「社会経済活動の継続」とのバランスを考慮しつつ、臨時情報が発表されたときの自らの行動を自ら判断し、あらかじめ決めておく。
引用は以上となります。
地方公共団体の防災対応(巨大地震警戒対応)の検討の章には、日常生活を行いつつ、一定期間、できるだけ安全な行動をとることが重要であり、住民が普段以上に地震に備えて警戒するという心構えを持つことができるよう、適切な周知啓発を行う必要があると記されています。壊れやすい建物等、危険性が高い場所をなるべく避けることがより安全な行動の事例としてあげられていますが、大津市民会館大ホール及びホワイエには、国土交通省の告示において、大臣が定める技術基準に従い、脱落防止対策を講ずべきことが定められている特定天井が存在します。特定天井は「脱落によって重大な危害を生ずるおそれがある天井」と定義づけられており、耐震改修工事が行われていないのであれば、当該ガイドラインで示される「危険性が高い場所」に該当すると考えます。
南海トラフ地震臨時情報とは、南海トラフ沿いの想定震源域で一定規模以上の地震が発生した場合等に、続けて大規模地震が発生する可能性が平常時と比べて相対的に高まった場合に発表される情報です。先発地震の発生場所や規模等によって南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)や同(巨大地震注意)等が発表され、これを受けて国は情報の種類に応じた防災対応を呼び掛けることになります。
大津市民会館においては、平成19年に耐震補強工事が実施されていますが、大規模地震の発生によって特定天井が脱落した場合、施設利用者の生命に危険を及ぼす可能性があり、円滑な避難にも影響を及ぼすことが危惧されます。大津市は施設利用者の安全を確保する観点から、南海トラフ地震臨時情報が発表された場合を想定し、大津市民会館大ホール及びホワイエの立ち入りに関して、あらかじめ方針を決めておかれるべきと提言するものです。検討されるべき事項は多岐に渡ると承知していますが、施設設置者である大津市長には、南海トラフ地震臨時情報発表時、特定天井の耐震改修工事が行われていない、大津市民会館大ホール及びホワイエについては、危険性が高い場所であることを広く伝える責務があると考えます。
大津市には大津市民会館以外にも、生涯学習センター(アトリウム・客席)、北部地域文化センター(客席)、和邇文化センター(客席)など特定天井を有する施設が数多く存在します。既存不適格扱いとなっている特定天井の脱落防止対策は、市民の安全に関わる極めて緊急性の高い改修工事であり、これまでの間、質疑・一般質問の機会を通じて早期の対応を求めてきましたが、大規模地震はいつ、どのような状況のもとで発生するか分かりません。大津市民会館をはじめとする特定天井を有する市有施設を対象とした、南海トラフ地震臨時情報発表時における管理運営方針を策定することについて、見解を求めます。
3点目、びわ湖浜大津駅周辺の魅力向上とにぎわいの創出に向けた取り組みについて。大津市は令和3年度から4年度にかけて、びわ湖浜大津駅周辺市有施設の利活用の検討に係る調査を実施しました。大津市民会館、大津公民館、旧大津公会堂、スカイプラザ浜大津、大津市立図書館を対象として、施設利用者を対象としたアンケートならびに市民アンケートが行われ、
①建物の安全性・老朽度(耐震性、老朽度や不具合の現状、バリアフリーの現状について)
②利用状況と施設機能(貸室等の利用状況と稼働率、施設機能の陳腐化・更新の必要性について)
③エリアマネジメント(施設機能の浜大津周辺エリアにおける整理・連携の可能性について)の3つの視点に基づき、当該各施設の現況評価が行われました。大津市は大津市民会館における建物の安全性・老朽度について、「大規模改修、改築等による対応が望まれている」と評価しています。
同施設は開設されてから50年が経過しており、これまでの間、外壁改修工事や耐震改修工事、設備の修繕工事などが行われてきましたが、施設内におけるバリアフリーには課題が多く、構造上、図れる改善にも限りがあると認識しています。私の知る限り、滋賀県内においても老朽化の程度が著しい、大規模なホールを有する公共建築物です。大津市は令和4年9月16日に開催された大津市議会総務常任委員会において、今後の方向性を検討するにあたって、考慮する点を明らかにしています。
① 大津の文化拠点エリア、交流結節の有利性を活かす(興行適性の活用)
② 購買・飲食施設のスポット配置や市有施設との複合化を図る(周遊性の向上)
③ 駐車、エリア内移動の経路・手段の最適化を図る(駐車場不足への対応)
④ エリア内のホール機能、会議室機能を整理・再編する(機能配置の最適化)
⑤(仮称)新・琵琶湖文化館、大津湖岸なぎさ公園、大津港などとの相乗効果を高める(施設間の連携)
以上の5点です。
大津市は令和7年6月通常会議で私からの大地震・巨大地震発生時における災害対応力の強化をテーマとした議会答弁において、特定天井の耐震対策については、公共施設マネジメントの取組の中で進めており、施設のあり方検討を踏まえ、大規模改修等の対策の優先順位を見極めた上で、必要な対策を講じていくとの見解を示されています。先ほど申し述べた考慮する点を踏まえ、施設のあり方検討が進まなければ、耐震対策が図られていない特定天井を大津市は大津市民会館に有し続けることになると危惧するものです。
大津市はびわ湖浜大津駅の周辺エリアに新しい琵琶湖文化館が整備されることを契機として、このエリアを歴史文化の学びや文化芸術の創造の場とし、にぎわいを創出することを目指しています。また、滋賀県においては、日本一にぎわいのある「湖の港」を目指し、「大津港活性化・再整備基本構想」を策定し、滋賀県立琵琶湖文化館整備事業についても、令和9年12月の開設に向けて工事が進められています。
これまでの間、大津市はびわ湖浜大津駅周辺の魅力向上とにぎわいの創出を図るため、大津市民会館をはじめ、当該エリアに立地する市有施設の利活用と整備のあり方に係る検討をどの様な取り組みのもとで進めてこられたのでしょうか。耐震改修が行われていない特定天井を有する大津市民会館については、防災上の観点からも、早期に方向性を決定されるべきと考え、見解を求めます。
答弁:市民部長
1点目の特定天井に対する評価と耐震対策の実現に向けた取組についてでありますが、建築基準法第12条に基づく点検について、大ホールは天井裏から目視により点検を行い、ホワイエについては天井の劣化状況等を室内から確認しており、それらの結果から、一定の安全が確保されていると認識しております。今後の取り組み方針につきましては、庁内における公共施設マネジメントによる施設のあり方検討を踏まえ、市民会館についても、今後の方針を検討してまいりたいと考えております。
3点目のびわ湖浜大津駅周辺の魅力向上とにぎわい創出に向けた取り組みについてのうち、特定天井を有する市民会館の方向性の決定についてでございますが、市民会館については、現在において特定天井のみを改修することは現実的ではないことから、改修する予定はございませんが、安全確認の重要性は認識しており、特定天井に係る点検の頻度を増やして、きめ細かく安全確認を行ってまいりたいと考えております。
答弁:危機管理監
2点目の南海トラフ地震臨時情報発表時における施設管理運営のあり方についてでありますが、本市は、「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」において、防災対策推進地域に指定されていることから、「南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイドライン」に基づき、市民や事業者に対して命をまもる行動をとるよう促していく必要があります。さらに、特定天井を有する施設に限らず施設の管理者としては、利用者の安全確保を最優先に考える必要があることから、当該ガイドラインの趣旨に沿った対応を促してまいります。
答弁:政策調整部長
3点目のびわ湖浜大津駅周辺の魅力向上とにぎわいの創出に向けた取り組みについてのうち、これまでの市有施設の利活用と整備のあり方に係る検討についてでありますが、びわ湖浜大津駅周辺市有施設の利活用に関する調査・検討を行って以降、魅力向上及びにぎわいの創出につながるよう取組を進めてきたもので、今もその途上にあることから、引き続き周辺施設における新たな動きや人流の変化を見極めてまいりたいと考えております。
再質問
まず1点目、特定天井の損傷・劣化状況に対する評価と耐震対策の実現に向けた取り組みについてです。大ホールについては、天井裏から、また、ホワイエについては室内からと答弁をいただきました。損傷・劣化の状況を評価いただく上において、今申し述べていただいた調査のあり様というのは、大津市として適切なものであると判断されておられるのでしょうか。私、初問で(天井裏を)目視いただくことの重要性については、お述べをさせていただいておりますので、この点を踏まえて、改めてお聞かせをください。また、今後、きめ細かく安全性を確認していくとも答弁をいただいておりますが、具体的にどのような取り組みのもとで実現をされていかれるのでしょうか。改めて答弁を求めます。
次に2点目、南海トラフ地震臨時情報発表時における施設管理運営のあり方についてです。国から示されたガイドラインに基づいて、対応をされていくという考えをお示しいただいたと理解をさせていただきました。その上でなんですけれども、施設を設置する大津市として、あらかじめ、方針を定めておくことの重要性については、改めて再質問で申し上げるまでもなくご理解いただいていると思うのですけれども、今後大津市として、どのような検討なり方針を策定されていかれるつもりなのでしょうか。
先ほど、施設を利用される市民の皆様、事業者に対して、特定天井が耐震改修されないまま危険性が高まったとなった場合に、そのことの情報については、しっかりとお伝えをしていく必要があるのではないでしょうかという趣旨で質問、提言をさせていただきましたが、大津市として今後どのような取り組みをしていかれるのか、もう少し詳しくお聞かせいただけないでしょうか。
3点目、琵琶湖浜大津駅周辺の魅力向上とにぎわいの創出に向けた取り組みについてです。今も検討の途上にあるといった趣旨で答弁をいただいたものと理解をさせていただきました。確かに、新しい琵琶湖文化館が整備されれば人の流れ、変わることになろうかとは思うのですけれども。しかしながら、大津市が検討にあたって考慮すべき点を明らかにされてから、もう既に3年近くが経過をしています。検討されるにあたっては、市民会館を所管される市民部だけではなく、今、政策調整部長がご答弁いただきましたが、公共施設マネジメントの観点で申し上げれば総務部、また、都市魅力の観点で申し上げれば、都市計画部、また、初問で申し上げましたが、浜大津駅周辺には検討の対象となった、調査の対象となった様々な公共施設もございますので、全庁的な検討が不可欠になるというふうに考えます。
先ほどの初問において、これらの検討をどのような取り組みのもとで進めてこられたのか、質問させていただきましたが、私は市長・副市長のリーダーシップに大いに期待をさせていただくものです。今後どういった方針のもとで、改めて検討されていかれるのか、もう一度お聞かせいただけないでしょうか。
答弁:市民部長
所管事項について、改めてのご質問についてお答えさせていただきます。まず、点検は適切であるかどうかということでございますけれども、法に基づいて実施をしておりますので、適切であると考えております。一方で、点検をきめ細やかにすることについて、具体的にどうなのかということなのですけれども、安全性の確保、これは非常に大切なことだという認識は持っておりますので、これまで以上に頻度を短くするなど、きめ細やかな点検を実施していきたいということを今、検討しているところでございます。
答弁:危機管理監
再度のご質問にお答えします。まずですね、そもそも南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイドラインにつきましては、趣旨といたしまして、過去に先発地震が発生後に巨大地震が発生した事例があるということから、今後、当該地域で一定規模の地震が発生すれば、後発地震が来る可能性が高くなるということで、それに備えて、あらかじめ対応を決めておくことを求めるものというふうな認識をしております。つきましては、特定天井を有する施設のみならず、それに限らず、施設ごとにですね、利用者等の安全確保のための管理運営方針が定められていない場合につきましては、それを定めていただくこと。すでにある場合については、必要に応じて、その見直しを図っていただくこと、これを求めていくということを考えております。管理運営方針の中身といたしましては、施設の耐震性能や先発地震による損傷の程度によりまして、後発地震への備えとして、施設の利用に関する取り組みなど、あらかじめ検討いただくことを想定しております。
答弁:政策調整部長
再度のご質問についてお答えいたします。検討途上にあるということで、もう3年近くなっているので、全庁的な検討が必要というような再質問でございました。市有施設等の利活用につきましては、様々な取り組みを進めたところでございます。一方で、びわ湖浜大津駅周辺の市有施設の整備のあり方につきましては、初問でも申しました通り、引き続き周辺施設における新たな動きや人流の変化を見極めてまいりたいと考えております。
再質問
大きな地震が発生した際、当該特定天井がどのような状況にあるのか、まずもって点検いただく必要があると考えます。先ほど市民部長が答弁でホワイエは室内からとおっしゃられましたが、本来は点検口などから、天井裏をしっかりと点検をいただく必要があります。
また、ホールに関しても大変広いので、天井裏からのぞいても見る範囲がどうしても限られてしまいます。まずもって、市民の皆さま、利用いただく方に入っていただける状況かどうかということを、速やかに判断していただく必要がありますので、このことについても、想定をしておく必要があると私は考えます。この点を踏まえてあらためて、管理運営指針を策定するお考え、いかがでございましょうか。
最後、政策調整部長にご答弁いただきました、今後の検討のあり方についてです。もう少し具体的に課題認を識踏まえてご答弁いただけないでしょうか。
答弁:市民部長
あらめてのご質問にお答えいたします。今おっしゃっていただいたような、点検が必要なきっかけといいますか、時期につきましては、何らかの揺れが起こった後にですね、点検をする、これをやることは必要性はあると思いますので、関係機関とも相談しながら実施を検討する必要があると思っております。
答弁:副市長
再度のご質問にお答えいたします。議員のご指摘は前回から3年間経ったんだけれども、どのように進んでいるんだということだと理解をしております。この3年間の間に例えばですけれども、当時は今の琵琶湖文化館ができるということが決まっておりましたけれど、それ以外にもですね、例えば、琵琶湖疏水の船が実際大津港まで延伸をしていただいたりもしておりますし、最も大きいところでは、昨年度、滋賀県におきまして、大津港活性化再整備基本構想を立てていただいた。つまり、県の港湾区域においてもこれから大きな開発をしていこう、大きな賑わいをよんでいこうというようなフェーズに変わってきたと。そう意味では周辺の人の動きというのは大きく変わる様相を呈してきております。そういう意味では、現段階で最適な理想的なそれらを結ぶ経路というのは非常に難しい状況にありますので、引き続き検討が必要な段階だというふうに考えております。